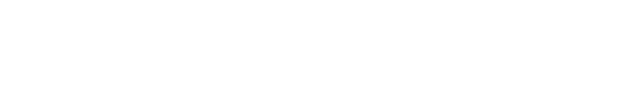糖尿病患者のアルコール摂取〜知っておくべき7つの注意点
糖尿病と診断されると、「お酒は完全に禁止なのだろうか」と不安に思われる方も多いでしょう。実際の診療でも、「お付き合いで飲まなければならない場面がある」「完全に断酒するのは難しい」といった声をよく耳にします。
結論から申し上げますと、糖尿病患者さんでも適量であれば飲酒は可能です。むしろ適度な飲酒は、ストレス解消やリラックス効果をもたらし、人間関係を円滑にする効果もあります。
しかし、糖尿病患者さんがアルコールを摂取する際には、血糖値への影響や合併症リスクを考慮した適切な飲み方を知っておくことが重要です。
本記事では、糖尿病専門医として10年以上の診療経験をもとに、糖尿病患者さんが安心してお酒を楽しむための7つの注意点をご紹介します。
糖尿病患者とアルコールの関係
「酒は百薬の長」ということわざがある通り、適度なアルコールは健康に良いことが知られています。しかし、糖尿病患者さんにとって、アルコールは血糖値に複雑な影響を与えるため、特別な注意が必要です。
アルコールと糖尿病の関係については、「Uカーブ」の関係があることが示されています。つまり、適度な飲酒をしていると血糖コントロールの状態はむしろ良くなり、糖尿病合併症も減るという報告があるのです。
日本人を対象とした大規模調査「NIPPON DATA」でも、2型糖尿病では、適度な飲酒をする習慣のある人は、まったく飲まない人に比べ、心血管疾患などの死亡リスクはむしろ低いという結果が報告されています。
しかし、適量を超えてアルコールを飲みすぎてしまうと、その健康効果はすぐに打ち消されてしまいます。アルコールを過度に飲むと、インスリン抵抗性の原因になり、糖尿病の管理が乱れ、高血圧や肥満のリスクも上昇します。
アルコールが血糖値に与える影響
アルコールは血糖値に複雑な影響を及ぼします。飲酒直後は血糖値が上昇することがありますが、その後、予想以上に血糖値が低下することがあります。
これは、肝臓がアルコールの分解を優先するため、血糖値を調整する機能が一時的に低下するためです。通常、血糖値が下がった時は肝臓でブドウ糖を作り出しますが、この機能が抑制されます。
特に、インスリンやSU薬などの血糖降下薬で治療を受けている方は、アルコールの急性効果として低血糖を起こしやすくなります。アルコールの代謝にともない、肝臓での糖新生(ブドウ糖の産生)が抑制され、血糖が下がりやすくなるのです。
糖尿病患者が知っておくべき適切な飲酒量
糖尿病患者さんが安全にお酒を楽しむためには、適切な飲酒量を知ることが重要です。厚生労働省の指針では、1日のアルコール摂取量の目安を、純アルコール量で約20g程度だとしています。
日本人の糖尿病患者さんでは、「適度な飲酒」は、男性でアルコール量が1日に20~25gぐらいまで、女性はその半分程度が目安となります。
これをアルコール飲料に換算すると、以下のようになります:
- ビール:中瓶1本(500ml)
- 日本酒:1合(180ml)
- 焼酎:0.6合(100ml)
- ワイン:グラス2杯(180ml)
- 缶チューハイ:1.5缶(520ml)
一般的に、純アルコール量で約20gを限度とするのが上手なお酒の飲み方といえるでしょう。酩酊状態となることなく、お酒を楽しみたいものです。
アルコール飲料の種類による影響の違い
アルコール飲料の種類によって、血糖値への影響は異なります。例えば、ビールには糖質が多く含まれているため、血糖値が上昇しやすい傾向があります。一方、ワインには抗酸化作用のあるポリフェノールが含まれており、適量であれば健康に良い影響をもたらす可能性があります。
特に赤ワインには、ポリフェノールの一種で抗酸化作用のあるレスベラトロールが含まれています。食事でアルコールを飲むのであれば、ワインは良い選択になる可能性があります。
「糖質ゼロ」「カロリーオフ」といった表示をしたビールや発泡酒などの酒類も店頭をにぎわしていますが、「糖質ゼロ」と表示してあっても、カロリーは「ゼロ」ではないので注意が必要です。
糖尿病患者のアルコール摂取における7つの注意点
糖尿病患者さんがアルコールを摂取する際には、以下の7つの点に注意することが重要です。これらを守ることで、安全にお酒を楽しむことができます。
1. 食事と一緒に飲む
食事をとらずに飲酒するのは避けると良いでしょう。空腹時の飲酒は特に危険で、低血糖を起こすリスクが高まります。
良質のタンパク質が多く含まれる魚や肉、大豆製品、ミネラルや食物繊維を多く含む野菜、とくに緑黄色野菜、海藻、キノコなどを食べながらお酒を楽しむことをお勧めします。
2. 適量を守る
先ほど述べた通り、男性で純アルコール20g、女性で10g程度を目安に、適量を守ることが大切です。飲みすぎは血糖コントロールを乱すだけでなく、肥満や高血圧などのリスクも高めます。
はじめは「少し」と思っていても、つい飲みすぎてしまうのがお酒です。食欲も同時に増し、食べ過ぎて肥満の原因になることもあります。
3. 低血糖に注意する
特にインスリン注射や経口血糖降下薬で糖尿病治療をうけている方は、低血糖が起こりやすくなるので注意が必要です。アルコールによる低血糖は、通常の低血糖よりも長時間続くことがあります。
また、アルコールの影響で低血糖の症状に気づきにくくなることもあります。飲酒後は血糖値をこまめに測定し、就寝前には必ず確認するようにしましょう。
4. 水分をしっかり摂る
アルコールには利尿作用があり、トイレが近くなります。排出された水分を補わないと、脱水状態になりやすいので、お酒を飲むときは、水分も一緒に補給するようにしましょう。
目安としては、アルコール1杯につき水1杯を飲むようにすると良いでしょう。これは二日酔いの予防にもなります。
5. 就寝前の飲酒に注意する
アルコールは寝つくまでの時間を短縮させるので、睡眠薬がわりに飲酒されている方も多いでしょう。しかし、就寝前に飲んだアルコールは、睡眠の後半部分を障害することが知られています。
つまり、寝つきは良いが夜中に目覚めてその後なかなか眠れない「中途覚醒」が起こりやすくなるのです。また、夜間の低血糖リスクも高まります。就寝の2時間前までには飲酒を終えるようにしましょう。
6. 薬との相互作用に注意する
2型糖尿病の治療に広く用いられているビグアナイド薬(メトホルミン)は、アルコールを過度に飲むと、副作用である乳酸アシドーシスが起こりやすくなります。
特に過度の飲酒を続けている人では、肝臓での乳酸の代謝能が低下しているおそれがあるので、注意が必要です。吐気・嘔吐・腹痛などの胃腸症状や呼吸が苦しいなどの症状がある場合は、すぐに医師に相談してください。
7. 定期的な休肝日を設ける
毎日の飲酒は肝臓に負担をかけます。週に2~3日は休肝日を設けて、肝臓を休ませることが大切です。これは糖尿病の有無にかかわらず、健康的な飲酒習慣として重要です。
アルコールが糖尿病合併症に与える影響
過度な飲酒は、糖尿病の合併症リスクを高める可能性があります。特に以下の点に注意が必要です。
血圧への影響
適量のお酒を飲むと、一般的に血圧が低下します。しかし、大量に飲み続けると、血管の収縮反応が高まり逆に血圧は上昇します。
毎日の飲酒量が多い人ほど血圧の平均値が高く、高血圧のリスクが上昇することが多くの研究で確かめられています。高血圧は糖尿病腎症などの合併症リスクを高めるため、注意が必要です。
神経障害への影響
アルコールの過剰摂取は、糖尿病性神経障害を悪化させる可能性があります。アルコールそのものにも神経毒性があるため、既に神経障害がある方は特に注意が必要です。
手足のしびれや痛み、感覚異常などの症状が強くなることがあります。
肝臓への影響
過度な飲酒は肝機能障害を引き起こす可能性があります。糖尿病患者さんは非アルコール性脂肪肝(NAFLD)のリスクが高いため、アルコールによる追加の肝臓への負担は避けると良いでしょう。
過体重や肥満のある方がアルコールを飲みすぎると、肝炎など肝機能障害になりやすいことも分かっています。
糖尿病患者におすすめの飲み方
糖尿病患者さんがアルコールを安全に楽しむためのおすすめの飲み方をご紹介します。
おすすめの飲酒パターン
食事と一緒に適量のアルコールを楽しむのが理想的です。特に夕食時に、ゆっくりと時間をかけて飲むことをお勧めします。
また、飲酒の前後には血糖値を測定し、自分の体がアルコールにどのように反応するかを知ることも大切です。特に就寝前の血糖値チェックは重要です。
おすすめの飲み物
糖質の少ないアルコール飲料を選ぶと良いでしょう。例えば、糖質の少ない焼酎や、ポリフェノールを含むワイン(特に赤ワイン)は比較的良い選択肢です。
ビールや甘いカクテル、果実酒などは糖質が多いため、摂取量に注意が必要です。また、「糖質ゼロ」と表示されている飲料でも、カロリーはゼロではないことを忘れないでください。
炭酸水で割って飲むことで、アルコール濃度を下げつつ満足感を得ることもできます。
まとめ:糖尿病患者のアルコール摂取
糖尿病患者さんでも、適量であればアルコールを楽しむことは可能です。むしろ適度な飲酒は、ストレス解消やリラックス効果をもたらし、心血管疾患のリスク低減にも寄与する可能性があります。
しかし、安全に飲酒を楽しむためには、以下の7つの注意点を守ることが重要です:
- 食事と一緒に飲む
- 適量を守る(男性で純アルコール20g、女性で10g程度)
- 低血糖に注意する
- 水分をしっかり摂る
- 就寝前の飲酒に注意する
- 薬との相互作用に注意する
- 定期的な休肝日を設ける
糖尿病の管理は個人差が大きいため、自分の体質や状態に合わせた飲酒習慣を見つけることが大切です。不安な点があれば、必ず主治医に相談してください。
当院では、患者さん一人ひとりのライフスタイルに合わせた「100人100通」のオーダーメイド治療を提供しています。管理栄養士がいるためお酒との付き合い方についても、個別にアドバイスいたしますので、お気軽にご相談ください。
適切な飲酒習慣を身につけることで、糖尿病とうまく付き合いながら、豊かな生活を送りましょう。
いんざい糖尿病・甲状腺クリニックでは、糖尿病専門医による個別相談も行っております。お気軽にご来院ください。
【著者情報】
院長 髙橋 紘(たかはし ひろ)

いんざい糖尿病・甲状腺クリニック 院長。
日出学園小学校、攻玉社高等学校を経て、埼玉医科大学医学部医学科を卒業。東京慈恵会医科大学大学院医学系研究科を修了し、医学博士を取得。
2010年より東京慈恵会医科大学附属病院にて初期研修を開始し、その後、糖尿病・代謝・内分泌内科を専門に臨床・教育・研究に従事。富士市立中央病院や東京慈恵会医科大学附属第三病院での勤務を経て、2023年からは同附属病院糖尿病・代謝・内分泌内科にて外来医長を務める。2024年6月、千葉県印西市に「いんざい糖尿病・甲状腺クリニック」を開院。
また、東京慈恵会慈恵看護専門学校や日本看護協会看護研修学校で非常勤講師として教育にも携わる。
資格・所属学会
医学博士
日本内科学会 総合内科専門医
日本糖尿病学会 糖尿病専門医・指導医
日本内分泌学会 内分泌代謝科専門医・指導医
日本肥満学会 肥満症専門医
難病指定医
小児慢性特定疾患指定医